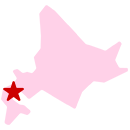本文
植木蒼悦プロフィール
更新日:2021年1月25日更新
印刷ページ表示
プロフィール
生誕~青年期
| 西暦 | 和暦 | 年月日等 | 年齢 | できごと |
|---|---|---|---|---|
| 1896年 | 明治29年 | 4月10日 | 0歳 | 父・植木善作、母・ワイの長男として函館市に生まれる。 |
| 1906年 | 明治39年 | 10歳 | 母・ワイが死亡、叔父・高桑馬之助に引き取られ、秋田県で過ごす。 | |
| 1908年 | 明治41年 | 12歳 | 秋田県立秋田中学に入学し、書・画・漢書に精通。 | |
| 1910年 | 明治43年 | 14歳 | 十和田湖を描きに来ていた木下藤次郎画伯が宿泊していた秋田の旅館を訪れ、師弟の縁を結ぶ。 | |
| 1913年 | 大正2年 | 17歳 | 秋田中学を卒業後、明治大学入学、並びに日本水彩画研究所に入所し、洋画技法を学ぶ。 | |
| 1914年 | 大正3年 | 7月 | 18歳 | 第1回二科展に油彩画を出展し、入選。 |
| 1915年 | 大正4年 | 10月 | 19歳 | 第2回二科展に油彩画を出展し、入選。 |
就職~結婚
| 西暦 | 和暦 | 年月日等 | 年齢 | できごと |
|---|---|---|---|---|
| 1916年 | 大正5年 | 20歳 | 父が事業に失敗し、やむを得ず明治大学を中退、日本水彩画研究所を退所。函館に帰郷する。 | |
| 1917年 | 大正6年 | 21歳 | 独学自活のため、函館税関鑑定課に勤務。文学・詩歌・哲学にも精進する。 | |
| 1928年 | 昭和3年 | 32歳 | 室蘭・小樽と転勤後、再度函館に帰郷。同年9月に藤本鎌次郎の長女・ヤサと結婚。門司税関鑑定課に転勤。 | |
| 1929年 | 昭和4年 | 6月 | 33歳 | 門司税関博多支所へ転勤。 |
| 1931年 | 昭和6年 | 3月 | 35歳 | 門司税関大連支所へ転勤。 |
本格的な活動
| 西暦 | 和暦 | 年月日等 | 年齢 | できごと |
|---|---|---|---|---|
| 1933年 | 昭和8年 | 5月 | 37歳 | 作家に専念するため依願退職し、函館市へ帰郷。以来、東洋画法の研究に没頭、画家生活に入る。 |
| 1936年 | 昭和11年 | 12月 | 40歳 | 山形県米沢市に転居。 |
| 1938年 | 昭和13年 | 42歳 | 函館市の今井デパートにて初めて日本画の個展を開催。 | |
| 1940年 | 昭和15年 | 2月 | 44歳 | 米沢市より函館へ帰郷。以後、永住する。同年9月に函館の絵画団体「赤光社」に入会。 |
| 1942年 | 昭和17年 | 46歳 | 函館市の今井デパートにて日本画の個展を開催。 | |
|
1947年 |
昭和22年 | 9月 | 51歳 | 函館大谷高等学校美術科担当講師として就職。主に書道を教える。 |
| 1948年 | 昭和23年 | 52歳 | 函館大谷高等学校60周年記念行事として、森屋デパートにて日本画の個展を開催。 | |
| 1952年 | 昭和27年 | 56歳 | 函館市土着の俳句団体「丘の句会」に入会、俳句に精進する。 | |
| 1954年 | 昭和29年 | 58歳 | 東京の俳句団体「雲」(佐々木有風主宰)に入会。佐々木有風の指導を受ける。 | |
| 1955年 | 昭和30年 | 59歳 | 函館市の森屋デパートにて還暦祝日本画展を開催。 |
晩年の活動~永眠
| 西暦 | 和暦 | 年月日等 | 年齢 | できごと |
|---|---|---|---|---|
| 1956年 | 昭和31年 | 5月 | 60歳 | 直腸癌のため、函館市立病院にて直腸摘出手術を受ける。 |
| 1960年 | 昭和35年 | 64歳 | 病のため、函館大谷高等学校を退職。 | |
| 1965年 | 昭和40年 | 69歳 | 函館市の森屋デパートにて古希祝日本画個展を開催。 | |
| 1969年 | 昭和44年 | 73歳 | 函館市文化賞を受賞。 | |
| 1975年 | 昭和50年 | 79歳 | 函館市杉並町の文雅堂画廊にて日本画の個展を開催。 | |
|
1982年 |
昭和57年 | 86歳 | 1月13日に病のため函館陵北病院に入院。2月10日、小康を得て本人の希望により退院。同24日、病状悪化のため再入院。3月10日午前4時58分永眠。 |
「河童」との関係
植木氏の晩年は、河童を題材にした水墨画の創作に時間を費やしました。しかし、画壇との関係を持たず、仙人のように孤独な生活を送っていたため、一般的にあまり知られないまま、昭和57年に永眠されました。
植木氏の作品は、対象を描きながら自らの生き方を問うという作風の作品が多く、河童画は植木氏本人の自画像とも言われております。
河童を描いた理由は、「昔の言い伝えで、河童は田畑を守る妖怪であり、弱い立場だった農民は、強い国家に抵抗する象徴として河童を崇拝していた。そこで反戦主義者だった植木氏は、軍国化を進める国家への抵抗のシンボルとして河童を見立て、自らの生き方に投影した。」と言われています。