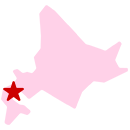本文
漁業コーナー
更新日:2021年1月25日更新
印刷ページ表示
丸胴(まるどう)

鰊・鰯などの締粕製造の圧搾胴。鉄枠に格子状に算木が通り、圧搾による油水が流出した。このタイプは左右に開閉する円筒型鉄枠のもの。
錨(いかり)

潮流や風により船が流れるのを停止させる錨。主に磯廻り漁のほか、ホッキ突き漁など箱眼鏡(ガラス箱)を利用する漁業で使用。「アンカー」とも言う。
背負いモッコ

船から魚を収蔵場所まで陸揚げするのに用いた背負運搬具。
魚鉤(さかなかぎ)

カレイやタラなど、漁獲された魚を扱った手鉤。片手で魚の頭部を刺すように用いた。長柄の魚鉤は、大型の魚を扱うときに用いられた。
へげ

沖揚げ作業で鰊などの魚を汲み取るほか、乾燥した締粕の建詰め作業などでスコップのように用いた。
やす

平やす(左)は磯廻り漁で箱眼鏡(ガラス箱)を見ながら、カジカ、ソイ、アブラコなどを突き刺す用具。やす先は3本でアゲ付。かごやす(中・右)は主に穴の周囲で休息しているタコやカジカ、アブラコなど捕獲するために使用された。やす先3本アゲ付き。
※その他、多数展示しております。