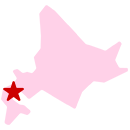本文
住宅用火災警報器設置後の維持管理について
定期的に作動するかどうか点検しましょう。
定期的(1ヶ月に1度が目安です。)に、火災警報器が鳴るかどうか、テストしてみましょう。また、長期に家を留守にしたときも、火災警報器が正常に動くかテストしましょう。点検方法は、本体のひもを引くものや、ボタンを押して点検できるもの等、機種によって異なりますから、取扱説明書を見て点検方法を確認しておきましょう。
おおむね10年をめどに、機器の交換が必要です。
火災警報器の交換は、機器に交換時期を明記したシールが貼ってあるか「ピー」という音などで交換時期を知らせます。そのめどがおおむね10年です。10年以内に電池切れを知らせてくれる音やランプが付いた時には電池交換も可能です(あくまでも機器の交換は10年をめどにして下さい)。
詳しくは取扱説明書を確認してください。
火災警報器が鳴ったらどうすればいい??
火災警報器は、火災の火元から出る煙や熱に反応して火災が起きていることを知らせるものです。
鳴っていることに気づいたら、すばやく消火したり、消火できないときには避難して周囲に知らせることも必要です。ときには誤報もありますが、家庭で火災から命を守るために、警報器が鳴ったときに必要な行動についてもよく確認しておきましょう。
火災のとき
火元を確認し避難してください。119番通報や可能ならば初期消火を行ってください。
火災でないとき
たばこの煙や調理中の湯気、煙の出る殺虫剤などを使用すると警報が鳴ることがあります。対処方法として、警報音停止ボタンを押す(ひもが付いている場合はひもを引く)か室内を換気すると警報音は止まり通常状態に戻ります。
それでも警報音が止まらない場合はメーカーに問い合わせてください。
煙の出る殺虫剤を使用する時は?(煙式の場合)
燻煙式の殺虫剤等を使用する場合は、住宅用火災警報器が警報を発することがありますので、取外す、ビニール等で覆うなどしてください。(燻煙式の殺虫剤等を使用した後は、すみやかに元に戻してください。)
電池切れのとき
短い音でピッ・・・ピッ・・・と一定の間隔で鳴る場合は電池切れの注意音です。
(メーカーによって異なりますので必ず説明書を確認してください。)
電池を新しいものに交換してください。機種によっては機器ごと交換するものがあるため、その場合は新しい警報器に交換してください。
(わからない場合は、購入店へ問い合わせてください。)
※詳しい設置場所については、長万部町ホームページの「住宅用火災警報器」(←クリック)にも掲載されていますし、長万部町消防署予防係(2-2049)に問い合わせてください。
※一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページに「住宅用火災警報器の警報が鳴った時の対処方法」が掲載されました。このサイトには、取扱説明書がない場合でも、適切に維持管理できるよう、メーカー別の機種ごとに、警報が鳴った時の正しい対処方法等について記載されていますので参考にしてください。
一般社団法人日本火災報知器工業会ホームページ「住宅用火災警報器の警報が鳴った時の対処方法」<外部リンク>(←クリック)